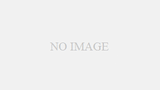今回は語る回だね。

はい!数学大好きな私が思いをぶちまけちゃいます!
(あくまで私の思いであることに注意してくださいね!)
なぜ数学は「定義」を大切にするのか
「数学は突き詰めると哲学になる」
この言葉を聞いたことはありませんか?
そう言われる理由は、数学で最も重要なものが「定義」だからです。
なぜ数学者は『1+1=2』すら証明したがるのか
なぜ数学が「定義」をこれほど重要視するのか?
答えは再現性です。
いつ、どこで、誰が計算しても、必ず同じ結果になる。
この普遍性(不変性)は、厳密な「定義」があってこそ成り立ちます。
会議で『とりあえず』が飛び交う理由
こんな場面、心当たりありませんか?
- 「とりあえず、来月までに検討しましょう」
- 「とりあえず、関係部署に確認を」
- 「とりあえず、様子を見て進めます」
参加者は何かを決めた気になっている。
でも実際には何も決まっていない。次回の会議でも、また同じ議論の繰り返し──。
この現象の根本原因は「定義の欠如」です。
数学では「三角形とは、3つの頂点と3つの辺を持つ図形」と明確に定義します。
だからこそ世界中の数学者が「三角形」について議論するとき、全員が同じものを話しています。
ところがビジネス現場では、この「定義」が驚くほど曖昧。
「品質向上」「顧客満足」「効率化」「イノベーション」
これらの言葉が飛び交いますが、参加者それぞれが異なる意味で理解しています。
Aさんの「品質向上」とBさんの「品質向上」が全く違う、なんて日常茶飯事です。
だから「とりあえず」が必要になります。
定義が曖昧なまま行動を決めると、後で「そんなつもりじゃなかった」という混乱が生じるからです。
「とりあえず」は参加者の無意識的な自己防衛なのです。
「定義する力」を身につけると、会議が劇的に変わります。
- 「品質向上って、具体的に何を指標にするんですか?」
- 「顧客満足を測る基準は何でしょう?」
こんな問いかけができるようになります。
曖昧さを排除し、全員が同じ土俵で議論する──これが数学的思考が仕事にもたらす最大の価値です。
そして数学と切り離せないのが「論理学」
「逆」や「裏」を用いたトリックに騙されるな!
「東大生は勉強ができる」
これは多くの人が納得する命題でしょう。
では「勉強ができる人は東大生である」はどうでしょうか?
直感的に「それは違う」と感じるはずです。
でも意外にも私たちは日常で、この手の論理的誤りに頻繁に騙されています。
論理学では「AならばB」という命題に対して、3つの関連命題を定義します:
- 逆:「BならばA」
- 裏:「AでないならばBでない」
- 対偶:「BでないならばAでない」
元の命題が真でも、その逆や裏は必ずしも真ではありません。
真になるのは対偶だけです。
この知識があると、世の中の「もっともらしい話」がいかに論理的に怪しいかが見えてきます。
例えば:
- 「成功者は早起きしている」→「早起きすれば成功する」(逆)
- 「優秀な営業マンは話し上手だ」→「話し上手なら優秀な営業マンである」(逆)
- 「この製品を使った人は満足している」 →「この製品を使わない人は満足していない」(裏)
広告、YouTube動画、勧誘──あらゆる場面で「逆」や「裏」を使った誤誘導を見かけます。
論理学の基本を知るだけで、これらのトリックに騙されにくくなるのです。
「全てのユニコーンは読書が好き」は論理的に正しい?!
論理学の面白さを味わえる例を見てみましょう。
「全てのユニコーンは読書が好きである」
この命題は真でしょうか、偽でしょうか?
多くの人は「なんとなく偽かな?」と考えるかもしれません。
しかし論理学としては、この命題は真なのです。
なぜか?
論理学では「全てのAはBである」は「Aに属する個体で、Bでないものは存在しない」という意味です。
ユニコーンは存在しません。(存在しない。とします笑)
だから「読書が好きでないユニコーン」も存在しません。
したがって、この命題は真なのです。
これは「空集合に関する命題は常に真」という論理学の原理です。
この考え方はプログラミングで重要になります。
「空のリストがTrueを返す」処理で、まさにこの論理が使われています。
日常生活に適用すると
「我が社の全赤字部門は改善計画を提出している」
この報告を聞いたとき、もしかすると赤字部門が存在しないだけかもしれません。
論理学を学ぶと、世界はより精密で、時には意外な美しさを持った場所として見えてくるのです。
抽象化の力は、数学から仕事へと繋がる
数学の面白さは、もう一つのキーワード、「抽象化」にもあります。
データベースの基礎理論である「集合論」や、コーヒーカップとドーナツを区別しないと例えられる「トポロジー」は、その最たる例です。
コーヒーカップとドーナツが同じ?──数学の「抽象性」の面白さ
コーヒーカップとドーナツが「同じもの」だと言われたら、どう感じますか?
まず中学数学の「合同」と「相似」から考えてみましょう。
合同変換では:
- 長さ・角度・面積が変わらない
相似変換では:
- 角度・比率が変わらない
では、図形を伸縮自在なゴムで作ったと想像してください。
このゴムを自由に変形させます。切ったり貼ったりはしません。
変形前後で変わらない性質は何でしょうか?
それが「穴の数」です。
コーヒーカップには取っ手部分に穴が一つあります。ドーナツにも穴が一つあります。
どちらも「穴が一つ開いた形」という本質は同じなのです。
この「変わらない本質」を取り扱うのが「トポロジー」という分野です。
トポロジーは言わば「本質を見抜く学問」と言えるでしょう。
『本質を見抜く力』が決定的な差を生む
この「変わらない本質を抜き出す」考え方は、仕事でも大いに活かせます。
例えば:
- 複数の業務から共通手順を抜き出せば→作業の自動化
- チーム全員の共通の悩みを抜き出せば→マニュアルの作成
- 成功事例の共通要因を抜き出せば→再現可能な戦略
私たちの身の回りにある課題や成功の本質を抜き出すこと。
これこそが、数学的思考法の真骨頂なのです。
生成AI時代にこそ「数学」は必要
「いい感じって、なんだよ!」
生成AIの発展は目覚ましく、最近では「いい感じの資料を作成して」といった曖昧な指示でも、それらしいアウトプットを出してくれます。
ですが
「いい感じって、なんだよ!!」
と思うのは私だけではないはずです。
もし、単に「いい感じ」で仕事が完了するのであれば、指示を出す人間は必要ありません。
生成AIと協働するための人間の価値
これからの時代に重要なのは何でしょうか?
「私の中で良い資料とは○○、○○、○○です」
こんな明確な指示を出せる力こそが、今後ますます重要になってくるはずです。
生成AIがどんなに進化しても、「定義する力」は人間だけが出せる価値です。
数学が培う論理的思考力は、まさにこの「定義する力」の基礎となるものなのです。
勉強する「理由」も「目的」も要らない
「数学を勉強して何の役に立つの?」
こんな質問を投げかけられたとき、多くの大人は困ってしまいます。
そして「論理的思考力が身につくから」といった、もっともらしい理由を並べ立てます。
でも、本当にそんな理由が必要でしょうか?
ここまで見てきたように、数学は確かに実用的です。
- 定義の力は会議を変革する
- 論理学は日常の罠から私たちを守る
- 抽象化は複雑な問題の本質を見抜かせる
生成AI時代において、数学的思考の価値はむしろ高まっています。
しかし、これらはすべて「結果的に得られるもの」です。
数学の真の魅力
コーヒーカップとドーナツが同じだなんて、実生活では何の役にも立ちません。
でも、その事実を知ったとき、世界が少し違って見えませんでしたか?
「全てのユニコーンは読書が好き」が論理的に正しいなんて、明日の仕事には関係ありません。
でも、その瞬間、論理という美しいシステムに触れたような気がしませんでしたか?
人間は本来、知ることそのものに喜びを感じる生き物です。
子どもが「なぜ?」「どうして?」を連発するのは、それが役に立つからではありません。
知りたいから、分かりたいから──ただそれだけです。
数学を学ぶ理由
数学を学ぶ理由を「将来の役に立つから」に限定するのは、もったいない話です。
それは音楽を「リラックス効果があるから」だけで聴くようなものです。
音楽の本質はその美しさにあります。絵画の本質はその表現力にあります。
そして数学の本質は、宇宙の構造を記述する言語としての美しさと、人間の理性が到達できる最も純粋な真理への憧れにあるのです。
「なぜ数学を学ぶのか?」
その答えは意外にシンプルです。
数学は面白いから。
数学に限った話ではありません。
勉強を「手段」と捉えるのではなく、勉強することを「目的」にしてみませんか。