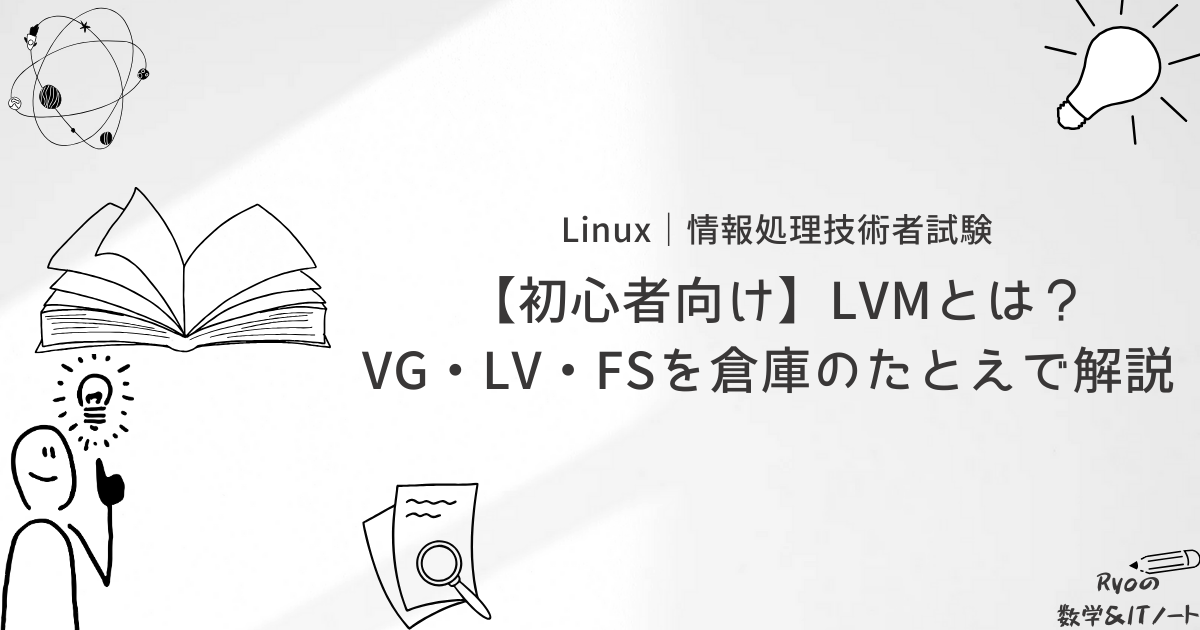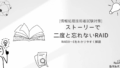ストーリーで覚える系の第2弾!
今回はLVMについてたとえ話で説明するよ。

Linuxの分野で出てくるキーワードですね。
確かに初めのころはなかなか理解できませんでした。

システム開発に慣れた人からすると、逆に分かりづらい例えになるかも(笑)
LVMとは?Linuxや情報処理技術者試験で押さえるべき基礎知識
サーバーやLinuxの運用では、ディスクの容量管理が大きな課題になります。
そんなときに役立つのが LVM(Logical Volume Manager) です。
名前だけを暗記すると混乱しがちですが、役割を整理すれば理解がぐっと楽になります。
ここではLVMの基本構造と、パーティションとの違いを解説します。
LVMの基本構造(PV・VG・LV・FS)を整理しよう
LVMを理解するには、4つの要素を整理するのが近道です。
- PV(Physical Volume):物理ディスクをLVMで扱えるようにしたもの
- VG(Volume Group):複数のPVをまとめた「大きな器」
- LV(Logical Volume):VGから切り出した利用単位。実際にマウントして使う
- FS(File System):LVの上に作成し、ファイルを管理する仕組み
つまり流れは「ディスク(PV)をまとめ(VG)、必要に応じて切り分け(LV)、最後に整理棚を置く(FS)」という形になります。
ポイントは「FSがあって初めて、ユーザーがファイルとして扱える」ことです。
パーティションとLVMの違いは?初心者が混乱しやすいポイント
LVMを学び始めると、パーティションとの違いが混乱ポイントになります。
- パーティション
- 物理ディスクを固定的に分割する方式
- 一度区切るとサイズ変更は困難
- LVM(LV)
- 必要な分だけ柔軟に切り出せる
- 後から容量を増減できる
つまり「固定的に決めるか」「柔軟に変えられるか」が大きな違いです。
Linuxの実務では、将来の拡張を考えてLVMが好まれるケースが多いです。
✅ 第1章のまとめ
・LVMはLogical Volume Managerの略で、柔軟なディスク管理を実現する仕組み
・PV・VG・LV・FSの流れを押さえると理解が進む
・パーティションは固定的、LVMは柔軟という違いがある
たとえ話で理解するLVM
ここまでで、LVMの基本構造やPV・VG・LV・FSの役割について学びました。
しかし、文字だけで理解すると少し抽象的で、初心者の方にはイメージしにくいかもしれません。
そこで、LVMの仕組みを身近なたとえ話で解説します。
物語の主人公は「リナ君」です。
リナ君が倉庫の使い方を考えているところを想像して、PVからFSまでの流れを整理していきます。
PV=倉庫:物理ディスクそのもの
リナ君は、土地に2つの「倉庫(PV:Physical Volume)」を置きました。
倉庫Aは100㎡、倉庫Bは200㎡
ただし、このままではそれぞれ独立しており、「100㎡」「200㎡」の単位でしか使えません。
「120㎡」のスペースが欲しいとき、倉庫Aでは足りないし、倉庫Bでは広すぎて余ってしまいます。
これが物理ディスクを直接使うときの制約にあたります。
VG=大倉庫:複数の倉庫をまとめて使いやすく
そこでリナ君は、複数の倉庫をつなげて「大倉庫(VG:Volume Group)」として管理することにしました。
倉庫Aと倉庫Bをまとめて、合計300㎡を「ひとつの大きな空間」として扱うことにしたのです。
これなら、必要に応じて自由にスペースを切り出せます。
- 120㎡の部屋
- 150㎡の部屋
- 残りはあとで別用途に
Linuxで複数のディスクをまとめて柔軟に活用できるのがVGの役割です。
ここで、次のような質問が浮かんできます。
最初から大きな倉庫(大容量ディスク)にしておけば?
確かにそうなのですが、現実には予算やタイミングの制約で大小さまざまな倉庫(ディスク)を後から追加していくことが多いです。
VGを使えば、そのような状況でも“ひとつのまとまった大倉庫”として扱えるため、将来的な拡張がとても楽になります。
LV=部屋:必要な広さを切り出す
次にりな君は、大倉庫の中を仕切って「部屋(LV:Logical Volume)」を作りました。
- 部屋1(120㎡):商品の在庫置き場
- 部屋2(150㎡):資材置き場
大倉庫(VG)の中から必要な分だけ切り出せるので、無駄なく活用できます。
さらに、必要に応じて部屋を拡張・縮小できる点がLVMの大きなメリットです。
FS=棚:整理して取り出しやすくする仕組み
最後にA君は、部屋の中に「棚やロッカー(FS:File System)」を設置しました。
棚を置くことで、物をきちんと分類・整理できるようになったのです。
もし棚がなければ、部屋の中はモノが散乱し、どこに何があるのか分からなくなってしまいます。
ファイルシステム(FS)は、この「整理整頓の仕組み」にあたります。
✅ まとめ:倉庫の物語で整理しよう
・PV=倉庫 … 物理ディスクそのもの
・VG=大倉庫 … 複数の倉庫をまとめて容量を柔軟に利用
・LV=部屋 … 必要な広さを切り出す。拡張・縮小も可能
・FS=棚 … 部屋の中で整理整頓する仕組み
いかがでしょうか。
システムの世界に慣れている人は、倉庫の例を出すより直接理解した方が早いかもしれませんね。
まとめ:倉庫の物語でLVMをイメージすれば理解が深まる
用語だけでなく「役割のイメージ」を押さえることが大切
この記事では、LVMの基本構造であるPV・VG・LV・FSを、倉庫の物語を通して整理しました。
重要なのは、単に用語を覚えることではありません。
それぞれの役割をイメージできることが理解を深める鍵です。
- PV=倉庫(物理ディスク)
- VG=大倉庫(複数倉庫をまとめて容量を柔軟に利用)
- LV=部屋(必要な広さを切り出す)
- FS=棚(部屋の中で整理整頓する仕組み)