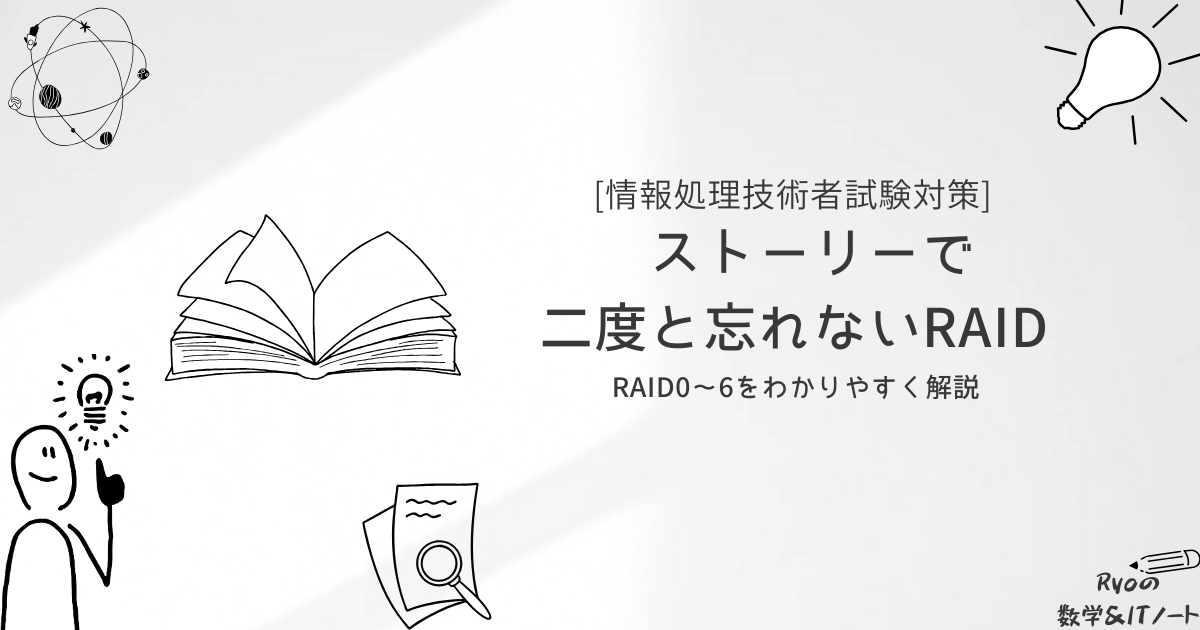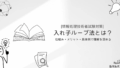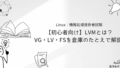今回のテーマは「RAIDの覚え方」だよ。

助かります。
資格勉強で一度覚えても、次に聞いたときに頭から抜けちゃってるんですよね。。

同じような思いを持っている人は多いんじゃないかな。
今回は基礎や覚え方に特化させているので
各RAIDの詳細にはあまり触れないことに注意してください!
RAIDの基本 — まず押さえるポイント
RAIDの目的
RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)とは
複数のハードディスクをまとめて1つの仕組みとして扱う技術です。
なぜわざわざ束ねるのか?その理由は大きく3つあります。
- 速度の向上:複数のディスクに分散して読み書きすることで、1台よりも速く処理できる。
- 冗長性(安全性)の確保:ディスクが壊れても、データを守る仕組みを持たせられる。
- 容量の拡張:小さなディスクを組み合わせて、大容量のストレージとして利用できる。
要するに、「速さ・安全・大きさ」をバランスよく得るための工夫がRAIDです。
誕生背景:1980年代のHDD事情と「安価なディスクを束ねる」発想
RAIDという考え方は、1980年代に生まれました。
当時は大容量ディスクが非常に高価で、研究者や企業は頭を抱えていました。
そこで
高価なディスクを1台買うのではなく、安価な小型ディスクを複数まとめればいいのでは?
という発想が登場します。
これがRAIDの原点です。
・高い性能がほしい → 複数の小型HDDで並列処理
・安全にデータを守りたい → コピーやパリティで冗長性を確保
・容量が必要 → 小さなHDDをまとめて大容量化
この発想が、後に「RAID0〜RAID6」という形で体系化されました。
RAID0〜6の特徴を一目で:用途別の早見表
ここでRAID0〜6の全体像を、シンプルな表でまとめておきましょう。
| RAIDレベル | 特徴 | 速度 | 安全性 | コスト効率 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAID0 | データを分散して高速化(ストライピング) | ◎ | × | ◎ | 処理速度重視(キャッシュ用途など) |
| RAID1 | データを丸ごとコピー(ミラーリング) | △ | ◎ | × | 重要データの保護 |
| RAID2〜4 | 初期の試行(誤り検出や専用パリティ) | △ | △ | × | 実用は少ない |
| RAID5 | 分散パリティで効率的に保護 | ○ | ○ | ○ | サーバーや一般業務システム |
| RAID6 | 二重パリティでさらに堅牢 | ○ | ◎ | △ | 大規模システム、重要データ保管 |
✅ 第1章のまとめ
・RAIDは「速さ・安全性・容量」をバランスするための技術
・1980年代の「安いHDDを束ねる」発想から誕生
・RAID0〜6はそれぞれ得意分野が異なる
ストーリーで覚えるRAID
プロローグ:研究者たちと安価なディスクたちの反乱
舞台は1980年代。
高価で高性能なディスクと、安いけれど非力なディスクが並存していた時代。
研究者たちは考えました。
安いディスクを束ねて、夢のストレージをつくれないか?
こうしてRAIDの物語が始まります。
RAID0(スピード狂)& RAID1(守護者):速さと安全、二者択一の起源
RAID 0:スピード狂の挑戦者
最初に登場したのは「速さ命」のスピード狂。
「データをバラバラに分けて同時に書き込めば、速くなるじゃないか!」
確かに彼は速い。誰よりも速い。
でも、事故に遭ったら一巻の終わり。
1台でも壊れたら、全部のデータが消えてしまう。
RAID0 = スピードは最強、でも命綱なし
RAID 1:用心深い守護者
次に現れたのは「安心第一」の守護者。
「速さなんかより、壊れても大丈夫な仕組みが欲しい!」
彼は同じデータを2台にコピーして守る。
まるで大切な書類をコピーして、2つの金庫に保管するように。
ただしコストは2倍かかる。
でも安心感は絶大。
RAID1 = ミラーリング。安全性の代名詞
RAID2〜4(試行錯誤の兄弟):ビット→バイト→ブロックの実験譚
「速さも欲しいし、安全も欲しい」
研究者たちはさらに考えます。
「データをもっと細かく分ければ効率的に守れるんじゃないか?」
初めにコンピューターの処理の単位である、ビット単位まで細かく分けました。
しかしそれはあまりにも効率が悪かったため、バイト単位→ブロック単位と分け方を大まかに。
- RAID2:ビット単位まで分割 → ケーキを砂糖粒にまで砕いて分けるような非効率さ。
- RAID3:バイト単位に分割 → 少し現実的になったけど、パリティを1人に押しつけすぎて疲弊。
- RAID4:ブロック単位に分割 → さらに改善したが、やはり「パリティ係」が過労死寸前。
彼らは挑戦的だったが、結局、現実には使いにくかった。
RAID2〜4は“過渡期の実験”。研究の遺産
チームワークと保険:RAID5とRAID6
RAID5の登場:分散パリティで「みんなで助け合う」仕組み
続いて登場したのがRAID5。
彼はこう言います。
「パリティを1人に任せるから疲れるんだ。みんなで分担しよう!」
データもパリティも全員で持ち合い、誰か1人が倒れても全員で助け合う。
速さ・容量効率・安全性、そのバランスが絶妙。
RAID5 = 効率的なチームワークで信頼される万能選手
RAID6の登場:二重パリティという“二重の保険”の意味
RAID6は、RAID5をさらに進化させた慎重派です。
- パリティを二重に分散して記録
- 2台まで同時に故障してもデータは守れる
- 書き込み時の計算が増えるため、速度はRAID5よりやや低下
物語に置き換えると、「チームに二重の保険をかける守護者」。
大規模システムや、データ損失が致命的な環境に向いています。
実務&試験での使い分け:情報処理技術者試験/データベース運用での判断基準
RAID5とRAID6は、実務でも試験でも区別が重要です。
- RAID5を選ぶ場面
- 読み込みが多いサーバー
- 容量効率を重視したい場合
- 1台故障までOKな環境
- RAID6を選ぶ場面
- データ損失のリスクが極力許されない環境
- 大規模システムで同時故障の可能性がある場合
- コストより安全性を優先する場合
試験では、「RAID5は1台故障まで、RAID6は2台故障までOK」という特徴がよく問われます。
データベース運用でも、この考え方が基本になります。
まとめ
RAIDの登場には、本記事のように壮大なストーリーが。。
あったかどうかは分かりませんが、覚えやすくなってはいませんでしょうか。