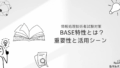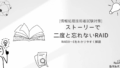今回は「入れ子ループ法」について解説していくよ!

名前からなんとなくの動きは掴めるけど、
いまいち深く理解できないあの処理ですね。
入れ子ループ法の基礎を理解する
入れ子ループ法とは?データベースで使われる結合アルゴリズムの一つ
「入れ子ループ法(Nested Loop Join)」は、データベースの結合アルゴリズムの一つです。
SQLで複数のテーブルを結合するとき、内部的にはどのようにデータを突き合わせるかを決める必要があります。その際に使われる代表的な方法の一つが、この入れ子ループ法です。
具体的には次のような流れで処理されます。
- あるテーブル(外側のテーブル)から1行データを取り出す
- その行に対応するデータを、もう一方のテーブル(内側のテーブル)から探す
- 一致すれば結合結果として出力
- 外側のテーブルの次の行に進み、同じ処理を繰り返す
つまり「外側のテーブルの1行に対して、内側のテーブルを毎回チェックする」という方式です。
プログラミングでいう二重ループ(for文の入れ子)を思い浮かべると理解しやすいでしょう。
💡 ポイントまとめ
・入れ子ループ法は、SQLのテーブル結合で使われるアルゴリズムの一つ
・外側テーブルの1行に対し、内側テーブルを毎回走査する仕組み
・「二重ループ」のイメージで考えると分かりやすい
入れ子ループ法の仕組みをイメージする
小さな繰り返し処理を重ねるイメージ
入れ子ループ法は名前の通り、「繰り返しの中に繰り返しがある」仕組みです。
日常の例で考えてみましょう。
- Aさんが「クラス名簿」から1人を選ぶ
- その1人の名前を「住所録」から探す
- 見つかれば「名簿と住所が結合した結果」として出力
- 次の人に移り、また同じことを繰り返す
このように「名簿を1人ずつ確認 → 住所録をすべて調べる」という流れになります。
つまり 小さな作業を繰り返し、積み重ねる のが入れ子ループ法の本質です。
実際のSQL結合でどう使われるのか
SQLで JOIN を実行すると、データベースは内部で結合アルゴリズムを選びます。
その候補の一つが入れ子ループ法です。
例えば:
SELECT 顧客.氏名, 注文.商品名
FROM 顧客
JOIN 注文 ON 顧客.ID = 注文.顧客ID;この場合、
- 外側テーブル(顧客)の1行を取り出す
- 内側テーブル(注文)を順番にチェックし、顧客IDが一致するものを探す
- 見つかれば結果に追加する
という処理が、すべての顧客について繰り返されます。
データ量による処理時間の違い
入れ子ループ法はシンプルな仕組みですが、データ量が増えると処理時間が大きく変わります。
- データ量が少ない場合:シンプルな処理なので高速に実行可能
- データ量が多い場合:外側テーブル × 内側テーブルの組み合わせが増えるため、処理が遅くなる
このため、実際のデータベースでは「インデックスを活用して内側テーブルの検索を高速化」する工夫がよく行われます。
💡 ポイントまとめ
・入れ子ループ法は「二重ループ」のように1行ごとに繰り返す仕組み
・SQLのJOIN実行時に使われる代表的なアルゴリズム
・データ量が増えると処理時間が急増する → インデックスの有無がカギ
入れ子ループ法のメリットとデメリット
他の結合方法(ハッシュ結合・ソートマージ結合)との比較
データベースは入れ子ループ法だけでなく、状況に応じて他の結合アルゴリズムも選択します。
- ハッシュ結合
- 結合キーをハッシュ表に変換して、高速に突き合わせる
- 大規模データに強い
- ソートマージ結合
- 両テーブルをソートし、順番に走査して結合
- 中規模~大規模に向いている
少量データに強い!入れ子ループ法のメリット
入れ子ループ法には、シンプルだからこその強みがあります。
- 少量のデータ結合では処理が速い
- プログラムとしての実装が簡単で、柔軟に使える
- インデックスを利用すると検索が効率化できる
そのため、数百件~数千件程度のデータであれば、入れ子ループ法はとても有効です。
資格勉強の観点では「小規模データに適する」と覚えておくと役立ちます。
大規模データでは不利になる理由
一方で、数百万件・数千万件といった大規模なデータになると不利になります。
理由はシンプルで、「外側テーブルの行数 × 内側テーブルの行数」という計算量が増えるためです。
例:
- 外側テーブルに 10,000 行
- 内側テーブルに 100,000 行
👉 最大で 10,000 × 100,000 = 10億回の比較 が必要になります。
こうなると実用的な速度は期待できません。
💡 ポイントまとめ
・入れ子ループ法は「少量データに強い」のが最大のメリット
・大規模データでは処理回数が膨大になり、速度面で不利
・ハッシュ結合やソートマージ結合と比較し、適材適所で使われる
まとめ
入れ子ループ法は、データベースの結合で最も基本的なアルゴリズムの一つです。
シンプルだからこそ理解しやすく、IPAの資格の中でも頻出のテーマとなっています。
この記事のポイントを整理すると:
- 入れ子ループ法は「二重ループ」のイメージで、外側テーブル1行ごとに内側テーブルを走査する
- 少量データではメリットが大きいが、大規模データでは不利になる
- ハッシュ結合やソートマージ結合と比較し、適材適所で使われる
特に試験では「計算量」に関する出題が多いです。
行数が n の二つの表を結合すると、最悪の場合 n × n = n² の計算量 になる、という点は必ず押さえておきましょう。